
COLUMN 2018.4.23
「聞くこと」について自由に語れるような、ひらかれた場をつくりたい
Makio KASHINO
幼少期からの電気工作と歌謡曲好きが昂じて聴覚研究者になったと公言する柏野牧夫氏。2017年からプロジェクトマネージャーを務める「Sports Brain Science Project(スポーツ脳科学プロジェクト)」も、もとはといえば趣味の投球が原点となっている。しかし通常、研究者が扱うテーマは、日常生活と何らかの意味で関連はしているけれど、その関係が直ちには理解できないものが多い。また、学術的な話は難しく、専門知識がなければなかなか理解できない。分野がちがえば、専門家どうしであっても互いに話が通じない。柏野氏は、そんな状況をなんとか変えていきたいという思いから「Hearing×」を立ち上げたと語る。
» READ MORE

COLUMN 2018.4.23
音楽とスポーツの密なる関係(前編)
- 楽器演奏の上達とスポーツの上達は似ている -
Shinichi FURUYA & Makio KASHINO
初回のゲストは、ピアニストの技術の向上など、音楽家に資する研究を手がける古屋晋一氏。かつてピアニストを志しながら、学生時代に部活でスポーツにも親しんできたという古屋氏は、「音楽の演奏とスポーツとは本質的な部分の問題意識が似ている」と語る。もとより聴覚の研究者として、脳における聴覚系と連関に興味を持ち続けてきた柏野牧夫氏が、古屋氏と身体技術向上の肝となる脳のはたらきについて、議論を交わした。
» READ MORE

COLUMN 2018.4.23
音楽とスポーツの密なる関係(中編)
- 左右の奇妙な非対称と局所性ジストニア -
Shinichi FURUYA & Makio KASHINO
古屋氏の代表的な研究の一つに、音楽家に発症する脳神経疾患である「局所性ジストニア」の治療法の開発がある。かつて古屋氏自身も「局所性ジストニア」を患い、治療法を開発したいという思いから研究者の道を歩むことになったという。じつは、この病気は、ゴルファーやピッチャーに発症するイップスと同じものであり、過度の訓練に起因する。局所性ジストニアが示唆する脳の特性について考察する。
» READ MORE

COLUMN 2018.9.5
コンピュータが音を聞き分けるということ(前編)
- 騒がしい環境下で世界一の音声認識精度を達成 -
Tomohiro NAKATANI, Shoko ARAKI & Makio KASHINO
人間の機能を模した深層ニューラルネットワーク(DNN)をつくることができれば、人間をより深く知ることができるかもしれない。しかし一方で、人間はかなり粗い情報から正解を導き出すことができたり、機械よりも圧倒的に少ない時間で言語を習得したりできる。はたして、機械は人間にどこまで近づくことができるのか。「情報」と「人間」を結ぶ新しい技術基盤の構築をめざすNTTコミュニケーション科学基礎研究所(CS研)の研究者たちが、現代科学の究極のテーマについて語り合う。
» READ MORE

COLUMN 2018.9.5
コンピュータが音を聞き分けるということ(中編)
- 深層ニューラルネットワークと人間の比較から見えてくるもの -
Tomohiro NAKATANI, Shoko ARAKI & Makio KASHINO
最近、深層ニューラルネットワーク(DNN)の登場で、音声認識の精度が一気に向上しつつある。しかしDNNの中身はブラックボックスになっていて、なぜ、そのような結果を導き出すのかがわからない。一方で、人間の音声認識のしくみ自体も、謎に包まれている部分がいまだ多くある。そうしたなか、近年、DNNで構築したモデルと人間とを比較する研究が注目されている。両者を比較することで、これまで謎に包まれていた人間の不思議が明らかになるかもしれない。
» READ MORE

COLUMN 2018.9.5
コンピュータが音を聞き分けるということ(後編)
- 機械との比較からわかる人間の特異性 -
Tomohiro NAKATANI, Shoko ARAKI & Makio KASHINO
NTTコミュニケーション科学基礎研究所の中谷智広さん、荒木章子さんらの研究グループでは、さまざまな音が混じり合った音声から、雑音などの不要な音を取り除きながらそれぞれの音を取り出す音源分離の技術や、音声認識の邪魔になる残響を取り除く技術の開発などを手がけている。最近では、深層ニューラルネットワーク技術を使った画期的な手法により、世界コンペティションで1位を獲得した。スマートフォンやスマートスピーカーの音声認識の向上に資する研究について話を聞いた。
» READ MORE

COLUMN 2019.12.11
身体技能のあくなき上達をめざして(後編)
- 学びに必要な条件とは -
Kazuo OKANOYA & Makio KASHINO
生物心理学者の岡ノ谷一夫さんは、学習には情動が不可欠であり、情動の喚起のカギを握るのは「場の共有」だという。ゆえに、現在、普及しつつあるMOOCはまだ不十分だと指摘する。さらに、現在、岡ノ谷さんが手がける「言語進化学」の研究における鳥やラットを使った研究の話を通じて、学びの本質について語り合った。
» READ MORE

COLUMN 2021.9.27
遠隔時代の身体(後編)
- 固有な身体性と遠隔コミュニケーションについて考える -
Asa ITO & Makio KASHINO
後編では、前編の伊藤亜紗さんのご講演に続き、柏野牧夫フェローと対談していただいた。両者とも、人間(身体)の研究をするうえで、出発点となっているのが固有な身体へのまなざしだ。人それぞれの違いに着目しつつ、共通項を見出していくことで、人間への理解を深めようとしている。多様な人間同士のコミュニケーション、とくにコロナ禍でデフォルトになった遠隔コミュニケーションについて、その課題と可能性について議論した。
» READ MORE
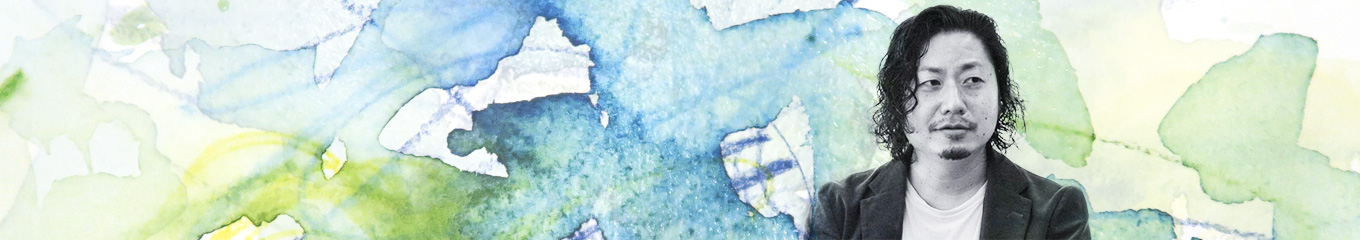
COLUMN 2022.3.15
ドラムと研究の両輪で、音楽と人間の本質に迫る(前編)
- 奏者からドラマー研究の開拓者へ -
Shinya FUJII & Makio KASHINO
今回のゲストである藤井進也氏は、ドラマー研究という新領域を開拓する若き研究者だ。藤井氏は大学時代、寝食を忘れるほどドラムに打ち込み、プロになろうかと迷いながらも、研究者の道を選択。プレイヤーの視点を持ちつつ、一流の奏者であるために何が必要なのか、良い音楽を奏でるとはどういうことなのかを、身体と脳の研究を通して追究している。柏野牧夫氏もまた、スポーツ脳科学の研究において、自ら実践者であることを旨としてきた。プレイヤー目線を持つ研究者同士が、共通の問題意識とめざすべき研究について語り合った。
» READ MORE

COLUMN 2022.3.15
ドラムと研究の両輪で、音楽と人間の本質に迫る(後編)
- 多様性のサイエンスから人間とは何かを解き明かしたい -
Shinya FUJII & Makio KASHINO
現在、柏野氏と藤井氏らは、ドラマーのジストニアをテーマに共同研究を進めている。ジストニアとは、自らの意思とは関係なく身体が動いてしまうなど、身体運動の制御ができなくなるという、ミュージシャン生命を脅かす難病だ。ジストニアに苦しむプロのドラマーを対象に、どういった状況下で症状が出るのか、そのときどのような神経活動が起こっているのかを明らかにして、メカニズムの解明に迫ることで、ジストニアや、スポーツの世界で問題となっているイップスの治療法につなげたいという。同時に、人間の多様性に焦点を当てつつ、リズムに合わせるという人間の特異な能力を通して、音楽と人の本質に迫る未踏の研究にも挑戦していく。
» READ MORE



 Top
Top